小松市稚松地区にあった小松城は、梯川の流れを引く水堀を複雑に
小松市
稚松地区に
小松市稚松地区に
あった小松城は、
あった小松城は、戻る1
内部リンク
張り巡らせた姿から「浮城」と呼ばれた。今や水堀はなく遺溝はわ
ずかだが、加賀藩3代藩主の前田利常がつくったまちの面影は残っ
ている。芦城公園の再整備計画で稚松が変わりゆく今、まちの礎を
外部リンク
見詰め直そうと、利常ゆかりの地を訪ね歩いた。
(小松高に「天守台」)
まずは小松高の敷地内にある本丸櫓台石垣に向かった。20メート
ル四方、高さ6メートルで「天守台」の通称で親しまれている。階
段から上ると、戻る2
段から上ると、小松のまちを一望できる。
小松のまちを一望、戻る4
近くのテニスコートでテニス部の練習に励む八田一輝生徒会長(1
7)=2年、小松市南浅井町=は「生徒にとって日常風景の一部。
上で弁当を食べることもある」と話す。我戸陽斗副会長(17)=
2年、加賀市山中温泉=は「天守台のある高校は全国でも珍しいと
思う。母校を説明しやすい」と胸を張る。
卒業アルバムの写真撮影スポットにも使われるといい、ある卒業生
の50代男性は「受験前に同級生と上ってガンバローと叫んだ」と
青春時代を振り返る。
「埋蔵文化財センターの」
埋蔵文化財センターの
微妙に色の異なる石が積まれた石垣は、デザイン性が高い。小松市
埋蔵文化財センターの川畑謙二所長は金沢の戸室石や小松産の鴨川
石などが使われているとし「色の配置も考え、ああいう積み方をし
たんでしょう」と説明してくれた。
川畑謙二所長は金沢の、戻る1
当時のままの場所にある小松城の遺溝は、この天守台と西側の石垣
の一部しかない。一般も見学可能だが意外と市民に知られておら
ず、稚松発信へ活用の伸びしろは大きそうだ。すでに石垣をモチー
フにした和菓子開発など、まちおこしに生かす動きが出ている。
「浮島の」天満宮
次に、利常が創建した小松天満宮に
次に、利常が創建した小松天満宮に
次に、利常が創建した小松天満宮に足を運ぶ。境内をぐるりと
堤防が囲み、梯川の流れに浮かんでいるように見える。この特
徴的な外観は2017年、文化財保護と治水を両立させた全国
初の「浮島化工事」によって整備された。
足を運ぶ。境内をぐるりと、戻る3
北畠能房宮司によると近年、小松城の絵図の新発見などを通じ
て、年貢米や塩を搬出入する水運ルートと関連施設の詳細が分
かってきた。ルートは小松天満宮近くを通ったという。
境内には、北前船船主が海上安全と商売繫盛を祈願して奉納し
た石像「願かけ撫牛」や、塩業者が奉納した灯籠が残る。北畠
ぐうじはこれらが、城下町のにぎわいを今に伝える証とみてい
る。「芦城公園に未来型図書館ができたら、かつての小松城の
様子を解説する動画を製作し、管内で流してはどうか」。北畠
宮司は、市に提言していく考えだ。
遺溝が少ない中、映像や動画をうまく使えば、まちの今昔を紹
遺構が少ない中、映像や動画を
遺構が少ない中、映像や動画を
介しやすいだろう。未来型図書館の整備をきっかけに、小松の
うまく使えば、まちの今昔を、戻る5
歴史を分かりやすく伝える取り組みも活性化すればいい。
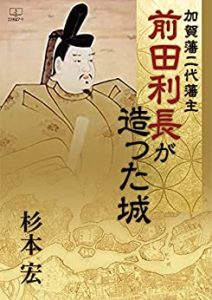
コメント以下に書いて下さい

