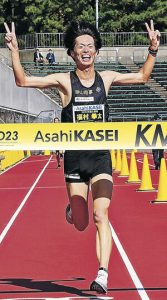能美市粟生町の手取川に架かる全長約400メートルの手取川橋。
内部リンク
旧国道8号沿いの金沢と小松を結ぶ交通の要衝で、トラックや車が
ひっきりなしに行き交う。ただ、明治中期まで橋は架けられておら
400メートルの手取川橋
外部リンク
(橋なく渡河は舟)
藩政期に旧北陸街道の整備が進められた一方で、加賀藩が戦略上の
観点から手取川には橋を架けさせなかった。粟生には代わりに慶長
年間に「粟生の渡し」が設けられ、旅人らが舟などで向こう岸に渡
った。
「春先や梅雨の時期は増水することが多く、何日も渡れずに足止め
を食うケースもあったようです」。能美ふるさとミュージアム学芸
員の鎌田康平さん(34)が解説する。
粟生町の歴史に詳しい粟生町会長の重田勝年さん(79)に案内さ
れ、手取川橋を訪れた。歩道が整備され、10分もあれば対岸の川
北町側に渡れる。橋のたもとには粟生の渡しの案内板も設置されて
いた。
「手取川は国内屈指の急流河川だ」
手取川は国内屈指の急流河川だ。まとまった雨が降り、普段より水
まとまった雨が降り、普段より、戻る1
かさが増した水面を見て、橋がない場合に安全に渡りきれるか、ま
ったく自信がない。暴れ川の脅威にさらされながらの渡河は、命懸
けだったに違いない。
ただ、幾度の水害にも負けずに集落を発展させてきた粟生の人々は、
逆境をプラスに変えた。川の増水によって、旅人は体を休める場所
を近くに求めた。農業が盛んだった粟生では、宿屋や飯屋に業態を
変える人が飛躍的に増えた。
「手取川が増水すると、粟生の村は繫盛する」。街道を行き交う人
はこの地の特性をこう表現したという。藩政期には集落の半数以上
に当たる145世帯が今で言う宿泊、飲食、物品販売業を営み、街
道筋に軒を連ねたそうだ。土地のハンディを商機に結び付ける人々
のたくましさが垣間見えた。
粟生に初めて橋が架けられたのは1888(明治21)年。鉄道の
開通も相まって川筋の宿泊需要は激減、今では宿場町の繫栄をとど
めるものは残っていない。重田会長は「往時のにぎわいがあったか
らこそ今の集落がある。語り継いでいきたい」と話した。
「のどかな田園地帯に、九谷五彩を」
(開業時は釣り堀主力)
のどかな田園地帯に、九谷五彩を模したカラフルな観覧車がそびえ
模したカラフルな観覧車が、戻る2
立つ。手取川沿いに立地する「手取フィッシュランド」は1967
(昭和42)年の開業当時、釣り堀が主力事業だった。
幹線道路沿いにあり、水温が保たれた手取川の伏流水が豊富に使え
る。これが立地の要因になった。今では3万坪もの敷地にジェット
コースターや各種アトラクションを備え、毎年30万人近くが訪れ
る。釣り堀コーナーは今でもリピーターがいる人気施設で、「遊園
地の多彩な楽しみ方を提供していきたい」辻本憲次会長(76)と
息子の勝彦社長(46)が力を込めた。
「藩政期から400年以上の時をへて」
藩政期から400年以上の時をへて、豊かな水資源を商機に生かす
豊かな水資源を商機に生かす、戻る3
取り組みは、旅人へのもてなしから県民なじみの遊園地を支えるま
でに結び付いた。この地の「川筋根性」は今、にぎわい創出への熱
意となって息づいている。粟生の川筋、難所が生んだにぎわい、遊
園地が水の恵み享受、橋なく渡河は舟。粟生へは仕事で何回か行っ
ています。手取フィッシュランドも子どもの頃連れていってもらい
ました。釣り堀ははっきり記憶しています。子どもができてからは
一緒に何回もいっています。とても楽しかったですね。乗り物がた
くさんありました。

コメント(以下に書いて下さい)